東レと産地企業らで作る東レ合繊クラスターは、金沢市内で第15回定時総会を開いた。
総会後の会見で宮本徹会長は、「創設から15年を迎え、理念の一つに掲げた『自立化』はある程度達成できた。今後は、『世界に類例のない原糸、高次加工一貫の連携体制を構築する』というもう一つの目標実現へ活動を強めたい」と抱負を語った。また、18年度の製品出荷額は155億円で前年より10億円伸ばした。
(中村恵生)
18年度の活動を振り返り、人材育成部会の活動、技術・素材開発部会とマーケティング推進部会による製販連携、総合展のレベルアップや海外市場向け販売の取り組みなど「各部会の活動が着実に進んだ」とし、宮本会長が14年の就任時に挙げた「グローバル活動の強化」「連携の多様化」「用途展開の進化、深化」の三つの課題も着実に成果が出ているとの認識を示した。
今後、製販連携による物作りや用途開拓を強化していくと同時に、その基盤となる人材育成にも引き続き力を入れていく。生産現場、営業担当、経営幹部と各層を対象にした講座を開いているが、「生産現場の5Sの前提として、19年度は営業を対象に考え方の5Sを浸透させたい」(滝川克己同クラスター理事人材育成部会長)という。
参加企業によって人材育成の取り組みに対する温度差もあるが、「トップが真剣に取り組まなければ進まない。クラスターとして経営者の理解を得るよう動いていく」(宮本会長)。
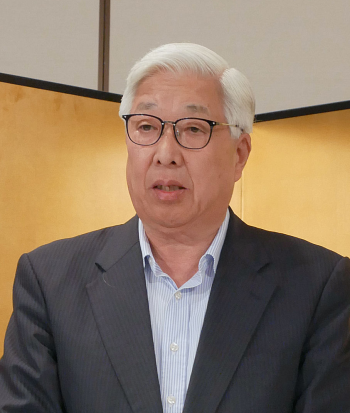
18年度製品出荷額は155億円と産地の生産規模が年々縮小する中で着実に伸ばし、13年度(86億円)から比較すると5年で8割増加した。環境配慮型ストレッチ「ヴァーチャレックス」をはじめ衣料向けが8割を占め、今後は非衣料も強化していく。海外販売は昨年からミラノウニカへの出展をやめてイタリアでの常設展示を開始し、成果が出ている。今年度は北米でもターゲットを2社に絞って攻勢をかけ、常設展示も検討する。
産地の共通課題では、物流の問題が顕在化しているが、「物流だけを切り出して解決しようとしても難しい。小ロット対応自体に限界があり、ロス削減や効率化、コストダウンなどサプライチェーン全体で連携していく必要がある」(宮本会長)とし、IT活用も含め、課題解決に引き続き取り組む。
また北陸産地の現状について、東レの鳥越和峰リーダー(東レテキスタイル事業部門長)は「海外が一貫生産体制なのに対し、日本は分業で掛け算の強みが出せる。垂直連携で開発につなげ、水平連携によってキャパシティー不足をカバーできる。これを加速すれば海外とも戦っていける」、安達一行サブリーダー(東レ常務生産本部長)は「日本は物作りの強みがあるが、開発などの速度は中国が圧倒的に速い。試作などをスピードアップし、現場のコスト競争力ももっと高めていかなければいけない」と今後の課題について話した。

