今年も残すところわずか。1年間のご愛読、まことにありがとうございました。毎号、欠かさずに掲載してきた「FB用語解説」の中から厳選してお送りします。初級・中級・上級の三つのクラスに分けてみました。ファッションビジネス用語の腕試しをお楽しみください。
◇アンサンブル
組み合わせて着ることを意図した服
ensemble。調和、統一、一緒になどの意味があり、音楽とファッションの業界でよく使われる。音楽では2人以上の調和のとれた合奏や合唱を指し、ファッションでは色や素材、柄などを調和させ、組み合わせて着ることを意図して作られたものを指す。
コートとドレス、ジャケットとドレス、ブラウスとスカート、カーディガンとプルオーバーなどの組み合わせが代表例。レディスのブラックフォーマルでは、ジャケットとドレスのアンサンブルが基本スタイルとして定着している。

◇ブランド
商標、特に名の通った銘柄
brand。商標、銘柄の意味。自社の製品を他社のものと区別するために付けた名称やシンボルのことで、特に、名の通った銘柄を指す。
語源は、牛に施した焼き印と言われる。ファッション業界では、ブランドという言葉の使用頻度が高く、ブランドビジネス、ラグジュアリーブランド、プライベートブランドなど様々な使い方がある。ブランドには、出所表示や品質保証、広告、財産権などの機能があるとされ、商標登録によって法的に保護される点も特徴。

◇SCM
生産・物流全体の経営管理手法
Supply Chain Managementの略。素材や資材の調達、商品の生産、小売りを通じて最終消費者の手に渡るまでの流れを総合的に管理し、全体の効率化や最適化を実現するための経営管理手法を指す。アパレル業界は素材や製品の生産過程が複雑で、多くの企業が関わっている。
また、素材調達や製品の生産は国内だけでなく、中国・アジアを中心に世界に広がっている。これを適切に管理することで、納期の短縮や生産・物流コストの削減、在庫の適正化につなげることができる。近年はIoT(モノのインターネット)技術を活用した管理が広がっている。

◇先染め
生地になる前の段階で染める
生地段階で染色する後染めに対して、生地になる前の段階で染色すること。通常は、糸を染める糸染め(yarn dyeing)を指すが、広い意味では綿や羊毛のわたを染める原料染めやばら毛染め、スライバーという縄状のわたを染めるトップ染め、短く切断する前の長繊維の束を染めるトウ染めなど、糸になる前の段階での染色も含まれる。
先染めは柄や深みのある色が出せる。チェックやストライプは代表的な先染め織物。先染めの糸を規則的に配置して織り上げる。

◇平場
ブランドの垣根を越えて品揃え
百貨店や大型専門店などで、壁に沿って造られた、いわゆる「ハコ」(箱型売り場)を除いた売り場のこと。ハコのような仕切りを設けず、全体を広く見渡せることからこのように呼ばれる。単一のアイテムで構成した単品平場、いくつかのアイテムを、統一したコンセプトやテイストで組み合わせたコーディネート平場がある。一般に平場では複数のブランドを販売する。「元(もと)売り場」「プロパー売り場」とも呼ばれる。

◇バファローチェック
黒いラインを重ねた大きな格子柄
buffalo check。赤や青、緑などをベースに黒いラインを重ねた大柄の格子柄を指す。ブロックチェックの一種。スコットランドの英雄とも義賊とも言われるロバート・ロイ・マグレガーが考案したと言われ、マグレガータータンやロブロイという別名もある。
ほかにも、猟師が山中で人と獲物の誤認を防止するために発案したという説など、諸説ある。この柄のウールシャツやジャケットを米国西部のカウボーイが着ることでよく知られる。ウェスタンスタイルが注目される18~19年秋冬メンズ・コレクションで、トレンド柄として浮上した。

◇SC
物販11店以上で構成する施設
ショッピングセンターの略。運営する企業(ディベロッパー)と出店企業(テナント)が不動産賃貸契約を結び、複数の店舗で構成される商業施設を指す。業界団体の日本SC協会では①小売業(物販)の店舗面積が1500平方メートル以上②核店舗を除くテナントが10店以上、などをSCの基準とする。
ファッションビル、駅ビル、地下街なども含まれる。SC協会によると、速報値で17年は48施設が開業し、総数は3217施設となり、総売上高は31兆9868億円(前年比2.1%増)に達した。18年は42施設前後が開業する予定。

◇ロット
生産や仕入れの最小単位
lot。生産単位、あるいは仕入れ単位のこと。一般的に製造ラインでは1回に生産する数量を決め、数回に分けて製造する。この1回の生産で出来上がった製品や出荷量をまとめて「1ロット」と呼ぶ。
素材メーカーで同じ素材を生産する場合、温度などの諸条件の違いから、完全に再現することが難しいため、「ロットが違うから発色が微妙に異なる」などと表現する。また、商売の量につながらない少量の時に「ロットにならない」などと使う。ミニマムロットの意味でも使われる。
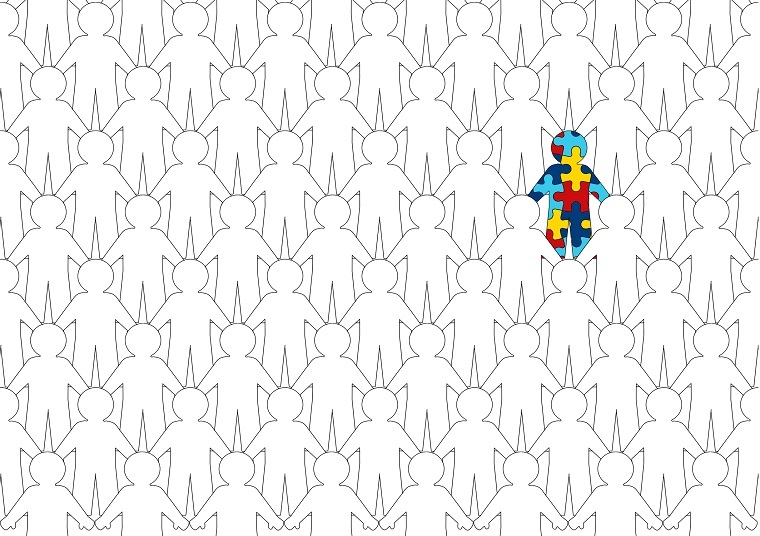
(誰もが納得、そだねー編につづく)
