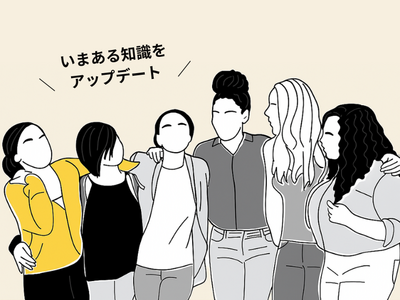ファッションビジネスにおいて、MD・販売・ECという3つの専門分野は常に密接に結びついています。MDが販売企画や展開計画を立て、それに合わせて店舗やECといった販路で販売を促進する。本来、この連動が欠かせません。
しかしながら現場では、互いの専門領域への理解が乏しいまま業務が進み、横の連携がうまく取れないこともしばしば。時には、足の引っ張り合いのような状況に陥ってしまうことさえあります。
もちろん、すべての分野を深く理解する必要はありません。ですが、隣接する業務を「ざっくり」でも理解しておくことで、仕事の精度は上がり、現場の動きも格段にスムーズになります。
この連載では、「なぜMD・販売・ECの連動が必要なのか」、そして「その連動によってどのような効果が生まれるのか」について、実例を交えながらざっくばらんにお話ししていきます。
■登場人物

MDコース講師:佐藤正臣
「数学は嫌いでも、算数はできるはず」でお馴染みのマサ佐藤。大手セレクトショップでMDを務め、現在はリテールMDアドバイザーとしてアパレルからライフスタイルブランド・スーパーマーケットなど、幅広い分野のマーチャンダイジング改善に従事。

販売コース講師:平山枝美
接客研修から顧客戦略の立案・推進、それに伴う接客方法・陳列・POP作成・マネジメントまで指導する販売コンサルタント。著書『売れる販売員が絶対言わない接客の言葉』は現在13刷達成!繊研plusで「間違いだらけの売場支援」を連載。

ECコース講師:深地雅也
ファッション・アパレルに特化したEC運用の支援に従事。得意とするのはGA4・BigQueryなどを活用したWEB解析の分野。年間計画立案からPL管理、CRM分析までECの販売計画に関わる領域を幅広くサポート。これまで80ブランド以上の運用に携わる。
どうして売場と本部は遠いの?
コミュニケーションの取り方を考える

販売から店長、エリマネ(エリアマネジャー)を経験してきて思うことがありまして…。いつまで経っても売場と本部って遠いなって感じるんです。私は「企業は顧客を作るためにある」と考えていて、そのためには戦略を立てて、会社のみんなが動いていくっていうのが理想だと思っているんですよ。

確かにそうですよね。僕も販売をやっていたからわかります。自分の経験談ですが、販売時代は「本部がー」といっていたのに、いざ本部に入ると人が変わるんですよね(苦笑)。
大切な仕事だし、やっていてよかったとは思っているけど、いまから販売をやれと言われたら、申し訳ないけどできないなぁ(汗)。

ですよねー。

でも、販売経験があるからこうしてMDの仕事ができるんだよなって思っていますよ。最近は販売経験せずにMDになれるところも多いし、学生も販売をやりたくない人って多いですよね。ECの人たちって、その辺はどう思ってるの?

EC側も当然ながら、常に売り上げをあげることを考えていますよ。だけど、全く販売の現場を理解している人がいないから、売場と連動できなくて(売り上げも)あがらないってことがすごく多いですね。

今まで支援に入った企業や学生たちには「MDは黒子であれ」って常々言っています。業界内にいると商品をつくっている側が花形に見えるけど、本部職は基本、販売職の裏方でしかないんですよ。
だって、お客さまへ商品を届けるのって売場でしょ。商品についての良いことも悪いことも全部受け止めるのは販売員。これって本部よりも圧倒的に大変。本部はそれを理解して、現場が動きやすい環境をつくることが大切。

そうですよね!お客さまが一番よく見ているのは、売場や販売員、ECサイトしかないですもんね。
そこで本部と上手くコミュニケーションするには、販売員サイドもECやMDとか、本部がどんな仕事をしているのか知ってもらわないといけないですね。

これまでMDの講義で「現場に行ってください!」とよく言っていたけど、そこで販売員に「いま何が売れてる」「お客さんは何が欲しいって言ってる」とか聞いているようじゃダメ。あれは売場にとって邪魔だから(笑)。
そうじゃなくて、販売員から「マサさん、この商品すぐにボタンが外れるんだけど…」とか「この商品、この数字ってどういう意味ですか?」とか、話しかけられるような関係性を築いていかないといけないんですよ。

次回は、意外に遠いECと売り場の不都合な真実についてお喋りします。
■Fashion Re:ducation
ファッション業界の教育事業「Fashion Re:ducation」。販売・MD・ECそれぞれの分野で活躍するスペシャリストが講師を担当。キャリアアップを目指す方、異なる専門領域を学びたい方、今のやり方に迷いを感じている方に向けて、現場ですぐに活かせる実践的な技術と知識を学べる講座を提供しています。